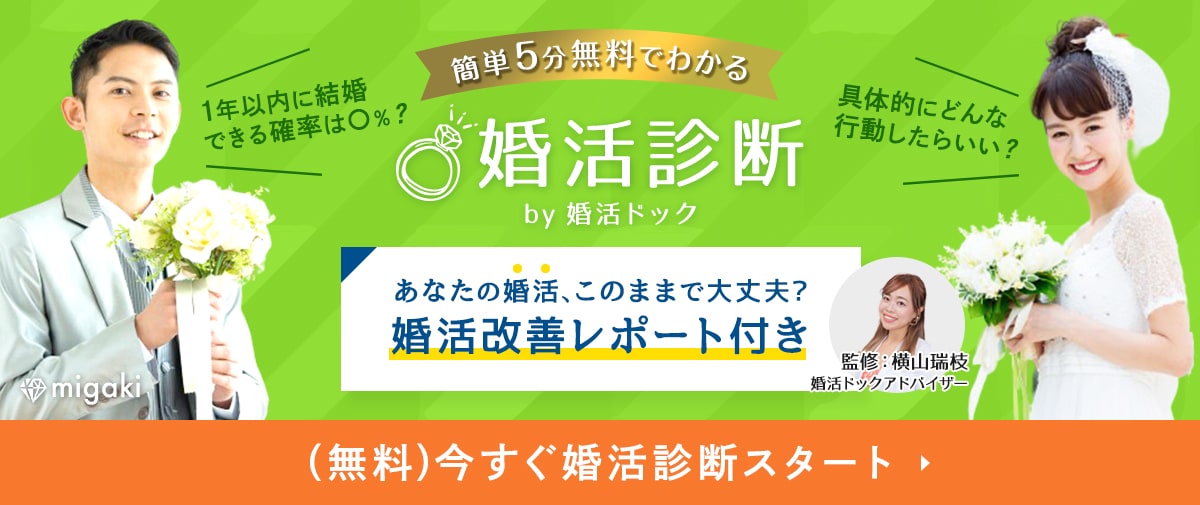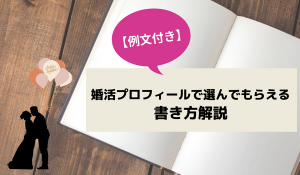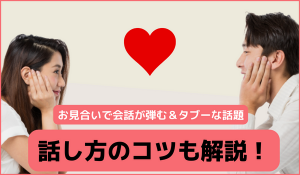法律上の結婚できる年齢には制限がありますが、実際に結婚をしたいと思う年齢は人によって異なります。
そこで今回は、
- 法律上の結婚できる最低年齢
- 結婚する人が多い男性・女性の年齢
- 結婚年齢は何歳?現実との違いについて
などについてご紹介します。
結婚できる最低年齢は何歳?
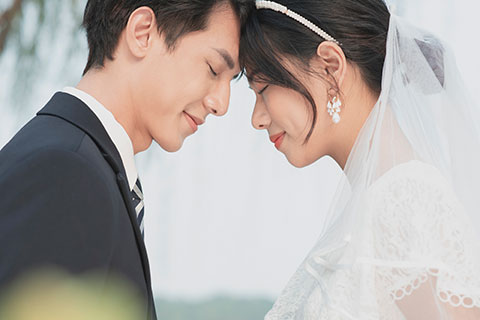
法律上、結婚ができる最低年齢は男性が18歳、女性が16歳からとなっています。
また、未成年者が結婚する場合には、親の同意が必要です。
しかし、2018年6月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、同時に男女の婚姻年齢も18歳へと統一が決まりました。
成年年齢と婚姻年齢の変更は2022年4月から施行されます。
ただし、改定された法律が施行されたあとも、2022年4月1日時点で16歳以上の女性については、18歳未満でも結婚することが可能です。
結婚する人が多い男性・女性の年齢は?


厚生労働省の調査によると、実際に結婚した人たちの初婚時の平均年齢は、平成7年の調査では男性が28.5歳、女性が26.3歳でした。
それに対し平成27年の調査では、男性は31.1歳、女性は29.4歳と初婚年齢が徐々に高くなっていることがわかります。
初婚年齢における男女の年齢差は、この20年間で2.2歳から1.7歳にまで縮まっていますが、女性の方が2歳程早く結婚している傾向があります。
また、男性の初婚平均年齢はやや遅いですが、再婚を含めて男女ともに最も多い結婚年齢は25歳〜29歳、次に30歳〜34歳です。
このことから、男女の年齢差はほとんどないことがわかります。
出典:厚生労働省「平成27年人口動態統計月報年計(概数)の概況」
結婚年齢は何歳?現実との違いについて


国立社会保障・人口問題研究所が2015年に調査した結果によると、独身者が希望する結婚年齢の平均は、
- 男性:30.4歳
- 女性:28.6歳
です。
またこの結果は、調査時点において各年齢層で男女ともにほぼ停滞状態にあったため、現在もほとんど変わらないことが予想されます。
10代から20代前半の頃には「早く結婚したい」と考えていた人も、社会に出て仕事をするようになると考えが変わることも多く、
- もう少し自由な時間を楽しみたい
- 仕事を始めたら結婚のことを考える余裕がなくなった
- 30歳くらいまでに結婚できればいい
など、結婚はもう少し後で良いと考える人もいるでしょう。
理想の結婚年齢は人によって異なります。
30歳前後での結婚希望が多いですが、その年齢で結婚して子供を産んだ女性の中には、「若いうちに結婚しておけば良かった」と後悔の声もあります。
民法改正で結婚できる最低年齢が下がると結婚はどう変わる?


2022年4月1日からは、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
これに伴い、親の承諾なしで結婚できる年齢が20歳から18歳になります。
民法の改正によって、今後の結婚はどのように変わっていくのでしょうか。
結婚ができる最低年齢は法律上男女ともに18歳
民法の改正により法律上、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられます。
これにより、女性は早く結婚するべきだという古くからの固定概念が無くなり、男女の平等性が高まることが期待できます。
中学校を卒業してすぐに結婚は認められなくなるため、「若気の至りで結婚してしまった」という後悔するケースは少なくなるでしょう。
男女ともに18歳なら親の承諾なしで結婚が可能
民法改正前の成人年齢は20歳です。
男性は18歳以上、女性は16歳以上であれば法律上結婚することは可能でしたが、未成年が結婚する場合は親の承諾が必要でした。
しかし、民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、男女ともに親の承諾なしでの結婚ができるようになります。
高校生でも18歳になれば親の承諾なしに結婚が可能となるため、学生結婚というケースも増える可能性があります。
早婚によるメリット・デメリット


2022年4月1日以降、男女ともに18歳になれば、親の承諾がなくても結婚することが可能です。
早く結婚したい人にとっては、親を説得する必要がなくなり自由に結婚することができるため、今よりも結婚しやすい状態になります。
しかし、早婚にはメリットだけではなくデメリットもあります。
結婚を決めるときは、結婚後の生活についてもしっかりと考え、慎重に判断することが大切です。
ここからは、早婚のメリットとデメリットをご紹介します。
早婚のメリット
早婚のメリットは、若いうちに子供が産めるということです。
妊娠・出産は年齢が高くなるほど難しくなり、晩婚化が進んでいる現在では、不妊治療を受けている方の数が年々増加傾向にあります。
また、体力のある若いうちに子供に恵まれれば、子育てにおいても体力面では有利です。
将来的にも、自分が若いうちに子供が成人することになるので、子供が独立した後の自由な時間を長く楽しむことができます。
早婚のデメリット
早婚のデメリットとしては、
- 経済状況が安定していない
- 社会経験が短い
- 精神面が大人になりきれていない可能性がある
などがあげられます。
社会人になり数年が経過していれば給与面でも安定してきますが、高校生や大学生のうちに結婚する場合は、収入がほとんどないことが予想されます。
妊娠をきっかけに結婚する場合でも、両親や祖父母などの経済的援助がなければ、2人の収入だけで生活することは困難です。
また、同世代が自由な時間を楽しんでいるときに、自分は子育てをしなければならない状態ということは、あらかじめ頭に入れておきましょう。
早婚にはメリットもありますが大変なことも多いので、
- 結婚後どのように生計を立てるのか
- 子育てをどのようにしていくのか
などを、しっかり考えたうえで結論を出すようにしましょう。
- 若いうちに子供が産めることが早婚のメリット
- 早婚のデメリットは、経済状況が安定していない・社会経験が短い・精神面が大人になりきれていない可能性がある
- 結婚後どのように生計を立てるのか、子育てをどのようにしていくのかなどをしっかり考えて結論を出す
結婚において年齢は大事なこと?


「早く結婚したい」「20代のうちに結婚したい」そんな風に考える方も多いでしょう。
ですが、結婚において年齢はそれほど大事なことなのでしょうか。
結婚とは、自分が選んだパートナーとの生活を始めるスタート地点であり、ゴールではありません。
早婚のメリットとデメリットをご紹介しましたが、「早く結婚=必ず幸せになれる」というわけではありません。
結婚後の生活は2人で作りあげていくものです。
- 結婚後の生活費やお金の管理は誰がするか
- 家事の役割分担について
- 子供ができた時の育児はどうするか
など、結婚後の生活について2人でしっかりと話し合ったうえで、本当に結婚したいと思えるお相手なのか冷静に判断しましょう。
\ 出会いの春に!月会費2ヶ月分無料キャンペーン /
4月18日(木)14:00から5月1日(水)13:59までのご登録で4月、5月の2ヶ月分の月会費が「0円」になるキャンペーンを実施中!
スマリッジでは「月会費2ヶ月分無料キャンペーン」を実施中!期間内のご登録で4月、5月の2ヶ月分の月会費が「0円」となります。
※U28割などお得な割引と併用してご利用できます。
期間:4月18日(木)14:00から5月1日(水)13:59まで
民法の改正により2022年4月1日からは、結婚できる最低年齢は男女ともに18歳となり、親の承諾がなくても結婚ができるようになります。
しかし、早婚にはメリットだけでなくデメリットもあります。
結婚を決めるときに最も大切なことは年齢ではなく、今後の人生を一緒に歩みたいと思えるお相手を見つけることではないでしょうか。
「18歳になったら結婚したい」「20代のうちに結婚したい」など早婚を希望する方のお相手選びは、結婚相談所の利用がおすすめです。
オンライン型結婚相談所「スマリッジ」は、店舗を持たないことで業界トップクラスの低価格を実現しました。
そのため、10代や20代の若い方でも婚活を始めやすいです。
また、婚活に関するお悩みや不安がある場合も、オンラインで気軽に婚活アドバイザーに相談することができます。
スマリッジであれば、早婚を希望する方や不安がある方へもしっかりとアドバイスをさせていただきますので、安心して婚活することが可能です。
入会相談も無料で受け付けていますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください